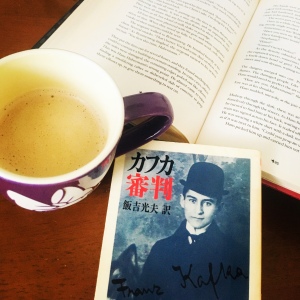 フランツ・カフカの長編小説『審判』をご紹介します。カフカの作品はこれまで、『変身』、『掟の前で』、『判決』、『アカデミーで報告する』、『城』を読んできました。『城』以外は全て短編です。また、『城』と今回読んだ『審判』はいずれも未完の小説となっています。残念ながら、類稀なる才能を持ったカフカの小説、短編以外は未完のものばかり。もったいないですね・・・。『城』に関しては、いきなりブチって終わってしまうので、カフカは最後どのような結末を用意していたのだろう・・・と永遠の謎を残してしまうのが本当に悔しい感じでした。対して、今回の『審判』は未完といえどもちょっと違います。というのも、結末まではしっかり描かれているのです。ただ、途中、ある章が未完で終わっている、という感じです。なので、未完といえば未完ですが、一応結末までは読めます。なので、『城』に比べるとモヤモヤ感はないですよ!
フランツ・カフカの長編小説『審判』をご紹介します。カフカの作品はこれまで、『変身』、『掟の前で』、『判決』、『アカデミーで報告する』、『城』を読んできました。『城』以外は全て短編です。また、『城』と今回読んだ『審判』はいずれも未完の小説となっています。残念ながら、類稀なる才能を持ったカフカの小説、短編以外は未完のものばかり。もったいないですね・・・。『城』に関しては、いきなりブチって終わってしまうので、カフカは最後どのような結末を用意していたのだろう・・・と永遠の謎を残してしまうのが本当に悔しい感じでした。対して、今回の『審判』は未完といえどもちょっと違います。というのも、結末まではしっかり描かれているのです。ただ、途中、ある章が未完で終わっている、という感じです。なので、未完といえば未完ですが、一応結末までは読めます。なので、『城』に比べるとモヤモヤ感はないですよ!
あらすじ
銀行員ヨーゼフ・Kは、ある朝とつぜん逮捕される。理由はいっさいわからない。判事にきいても、弁護士にたずねても、なぜこんなことになったのか、教えられないまま、二人の男に〈犬のように〉殺されてしまう。〈不可解〉を通して人間の核心にせまるカフカの代表作。
カフカの作品を読んだことがある人なら、このあらすじを読むと、フフフと笑ってしまうことでしょう。この感じ、いかにもカフカらしいじゃないか、と。私が一番初めに読んだのは『城』でしたが、その前に『変身』の内容はどこかで聞いて知っていたので、すでにカフカの作風はなんとなく知っているつもりでした。不可解、不条理、不合理、そんな世界をテーマに描く、おかしな物語の数々。『変身』の内容を聞いたとき、そして実際に読んだときは、なんでこんな意味不明な理解しがたい小説を描くのだろう・・・と不思議で仕方なかったのですが、『城』が予想以上に面白かったので、カフカのことを受け入れることができました。むしろ『城』はすごく好きな作品です。『審判』は『城』と非常に似ていると思います。『城』でも、測量士のKという人物が主人公なのですが、彼はとある「城」から雇われることになって、その「城」のあるとされる村まで行き、「城」を目指すという話。しかし、誰に聞いても「城」までの行き方がわからなかったり、挙げ句の果てには「城」から「あなたを雇った覚えはない」と言われてしまったり・・・。まさに、不条理の世界があふれたおかしな小説だったんですね。ま、とにかく、カフカの世界はいつも不条理の世界なのだ、ということを知っていれば『審判』もなんら不思議なことなく、受け入れることができるでしょう。
内容は、もうあらすじに書いている通りです。笑。銀行員のKがある朝とつぜん逮捕されちゃうんですね。二人の男がやってきて、逮捕状を見せられる、みたいな。Kは全く意味がわかりません。悪いことをした記憶もないし、しかも、男たちは訴状の内容を言うわけでもない。つまり、逮捕の理由が全くわからない、と言う意味不明な状況なのです。Kはあるアパートに住んでいます。そこの家主であるグルーバッハ夫人はKと親しい仲なのですが、この時ばかりは、よそよそしい態度で、全然Kを助けてくれる風もない・・・。同じアパートにはビュルストナー嬢という女性もいるのですが、どうやら彼女との関係が逮捕に関係しているらしいとか・・・?でも、結局理由はわからぬままなのです。しかも、おかしいことにKは別に連行されるわけでもないのです!逮捕を伝えてきた男たちには、銀行に行ってください、と言われる始末。Kは意味がわからないながらも、その日も普通に銀行に行って仕事をすることになります。逮捕されたけど、生活は元どおり・・・。意味不明すぎますね。
その後、「最初の審理」が行われます。予審判事に会いに行きます。裁判所ですね。しかし、その裁判所までの道中がどう考えてもおかしい。裁判所なんて普通、裁判所としての建物があるはずなのに、一般の住人も住んでいるようなアパートメントのようなところの一室が裁判所という・・・。そこまでたどり着くのにも時間がかかって、Kがやっと到着した頃には「遅刻したからもう審理はできない!」と言われたり・・・。会場もどことなく不穏な空気が漂っています。Kは判事に対して、不条理な逮捕劇への不満をつらつらと述べました。しかし、結局ここでも、Kは逮捕の理由を知ることができないのです。
後日、Kは裁判所から特に手紙などは届きませんでしたが、念のため審理があるかもしれないと考え、法廷へ。しかしその日は休み・・・。自分の部屋を裁判所に貸しているという、とある女と話をします。なんでもこの女には夫がいるのですが、法律を学んでいる学生と不倫中らしいです。この学生は権力があるのか、夫は不倫関係を知っていながらも何も言えないんだとか。その後、裁判所の事務局にもたどり着き、案内されたりするんですが、相変わらず不穏な空気が漂う世界でKは気分が悪くなり、逃げ出します。
さて、ある日のこと。Kはビュルストナー嬢の部屋に、モンタークという別の女性が引っ越してきたことに気づきます。実は、Kは逮捕告知をされた後に、一度ビュルストナー嬢と話をしたのですが、その時にいきなり彼女にキスをしたりして、彼女をドン引きさせていました。Kの置かれている状況は全くもっておかしいのですが、K自身も実はめちゃくちゃ変わった人物なのです・・・。で、Kは自分の無礼を謝りたいと思っていたのですが、ビュルストナー嬢からは完全に拒否られたのでしょう、引っ越しされてしまいました。
さて、どんどん進みましょう。次はKの叔父が事情を聞きにやってきます。噂でKの逮捕を知ったようです。叔父はKを心配して、友人の弁護士の元へKを連れて行ってくれます。助けを求めに行ったんですね。この弁護士、病気らしいですが、なんとか話は聞いてくれました。そこには弁護士の付添婦であるレーニという女性がいました。弁護士と叔父が色々話している間、Kはその部屋にいるのが嫌になってか、レーニの元へ行き、彼女とイチャイチャします・・・。突拍子も無い展開・・・。後から叔父と合流した際、こっぴどく叱られたK。弁護士に助けを求めに行っているのに、そこの付添婦といきなりいちゃつきだしたら、そりゃ怒られても仕方ない。K、やっぱり変人です。
お次は、ある工場主がKを訪ねに、銀行にやってきます。ちなみにKは業務主任という立場です。この工場主、ティトレリという画家と知り合いらしいのですが、この画家が裁判所と通じているらしく、噂でKの逮捕について知ったんだそうですね。そこで工場主は、ティトレリならKを助けてくれるかも?とわざわざ教えてにきてくれたんですね。Kは仕事を投げ出して、ティトレリに会いに行きます。まあ、Kもかなり切羽詰まってますからね。画家の家もまた、おかしな空気感漂う空間でした。そこでティトレリと色々話したK。ティトレリによると、Kが求めうる解決策は3つあるらしいのです。「真の放免、仮の放免、引き延ばし」の3つ。真の放免はその名の通り、完全に無罪判決となることだそう。しかし、これはほぼ不可能だとも言われてしまいます。少なくともティトレリの力では到底及ばない、と。では仮の放免は?ティトレリがKの無罪を証明する書類を用意して、うまく言えば無罪判決となる。ただ、しばらくしていきなりやっぱり撤回!となる場合があるらしく、真の放免とは言えない、という・・・。じゃあ最後の引き延ばしは?これは、訴訟がいつまでも最初の段階でとどめられていること、だそう。突然の逮捕の心配などはないけれど、継続的に裁判所に行かないといけないし、引き延ばしておけるに十分な理由もいるのだとか・・・。何れにせよ、Kが本当に求める「真の放免」は達成することができないという残酷な真実を知り、Kはティトレリのもとを去りました。
続いては第8章ですが、実はこの第8章が未完の部分になります。
Kはいつまでも行動に移ってくれない無能な弁護士に嫌気がさして、解約を申し出るために、弁護士を訪れます。そこで商人のブロックという人物と出会います。彼もまた、Kと同じ弁護士に助けてもらっているんだとか。しかも彼は5年間も訴訟で闘っているらしい・・・。また、他にも何人かの弁護士を雇っているらしいです。付添婦のレーニも再び登場しますが、この女もなんかおかしいんですよ。怖いです。なぜ不気味で怖いのか、説明は難しいのでぜひ読んでいただきたいです。とにかく、Kは無能かつ不気味な弁護士とレーニと離れるためにも解約を言い渡し、その場を去ります。ま、ここは未完なのでどういう風に終わらせるつもりだったのかはわからない章ではあります。
第9章。ある時、Kは知り合いのイタリア人を観光案内することになりました。大聖堂で待ち合わせをしたのですが、いつまで待ってもイタリア人は現れません。Kは突然、大聖堂にいた、ある僧に話しかけられます。この僧とは初対面なのに、なぜか僧はKの名前も、彼の置かれている状況についても知っているという恐怖。そして僧は「門番」と「男」の話をKに聞かせます。この話は、おそらく何かを比喩しているのだろうと思われるのですが、何を示しているのかはわからなかった。この話もまた、不条理な話なんです。「男」はある建物の中へ入りたいのだけど「門番」に入るなと言われてしまう。それから数年、あるいは数十年?、「男」は待ち続ける。最後に死にかけのところで、やっと「門番」は実はこの門は「男」のためだけに存在していたものだと打ち明ける、という話。なんの話や・・・とつっこんでしまいたくなるような不条理のお話。Kの置かれている立場を彷彿とさせるような話でもある。まあ、きっとこれにもなんらかの意味を、カフカは与えているに違いない、でも私にはさっぱりだった。
さて、第10章。最後の章です。Kの31歳の誕生日の前夜。Kが逮捕告知されたあの日は、Kの30歳の誕生日だったんです。ということは、逮捕告知されてから一年が経ったことになる。この一年、結局、Kは逮捕の理由を知ることなく、裁判が進むこともなく、弁護士に助けられることもなく、日々を過ごしてきた。そしてとうとう、二人の男に連行されてしまう・・・!ほぼ無抵抗のK。二人にがっちり捕まえられているのだから、抵抗したところで逃げることはできないだろう。そして・・・ついに・・・。
Kは、男に包丁で胸をつき刺され、処刑されてしまった・・・!!!!!
「まるで犬死にだ!」
これがKの最後の言葉。
そして物語は終わる。
なんという、恐ろしい世界をカフカは描くのだろうか・・・。最初から最後まで一切救いのない物語。せめて、Kの逮捕の理由、処刑の理由さえわかればもう少し納得もできたはずだろう。しかし、そこは描かないのがカフカなのです!不条理、不可解、不合理、これこそが、カフカの描きたいテーマなのでしょうね。あらすじを読めばわかるように、非常に不愉快で胸糞悪いと言ってもいいぐらいの内容です。それは『変身』でも同じでしょう。ある日突然虫になった男がむなしく死んでいく物語にも通じる世界観が『審判』にも流れています。ただ、当然無意味にこの小説を描いたとは思えません。解釈は様々にあるのですから。
訳者解説から引いておきます。
Kはある朝眼覚めたとき、この組織の人間に声を掛けられる。Kはおそらく、それを相手にしてはいけなかったのである。それに応対したことが彼らの組織に支配するトーンやペースに巻きこまれることを意味したのだから。しかし、この二人の男が所属していた組織とは、カフカの頭の中ではおそらく当時のチェコそのもの、つまり一九二〇年代のオーストリア帝政末期の半分腐りかけていた国家体制と緊密に結びついていたのだろう。当時のチェコにはふやけた官僚主義だけがはびこり、国民のひとりひとりはその犠牲者の観を呈していた。しかも、国民ひとりひとりはこの息苦しさから逃れることはできない。帝政下の一国に属している以上、彼はその国の法を後楯とした官僚組織の圧迫から逃れることができない。このことは法律を修めたカフカには分かりすぎるぐらい分っていた。そのために彼は、彼の作品の主人公Kを二人の男に代表される組織にいつのまにか巻きこまれていく運命に遭遇させる。(解説285)
長いですが、引用しておきました。この作品を理解するためには必要な部分だと思いましたので。カフカの生まれた国、オーストリア=ハンガリー帝国の当時の情勢については全然知らないのでなんとも言えませんが・・・。つまりは、Kの置かれた、「帝国という巨大組織に属す一国民である以上、そこから逃れることのできない不条理な状況」というのは、カフカのみならず、すべての国民の元に覆い被さっていたものなのだということでしょうか。Kはカフカ自身であり、また、多くの国民のことを指している、と。官僚組織から言われたことは、たとえどれほど不合理なものであっても受け入れるしかない。誰も助けてくれないし、納得のいく理由を教えてもらえるわけでもない。まさに組織の犬で、犬のように死んでいくしかないのか、と。そう考えると、この『審判』という一見意味不明すぎる作品も、恐ろしいほどにリアルな国家批判の小説ということがわかってきますね。
そして、今回初めて気づいたことがありました。以前、『変身』を含む短編集を読んだ時に『掟の前で』という短編も読んだことがあったんです。しかし、完全に内容は忘れていました。なんと、この『掟の前で』は『審判』の中に出てくるあるエピソードを独立させたものだったんですね!第9章、大聖堂にて僧がKに話してくれたあの「門番」と「男」の話です。これを読んでいる時は全く気付きませんでしたが、『掟の前で』というタイトルは覚えていました。なるほどー、あれとこの話は同じものだったのか!当時読んだときは『掟の前で』についての感想を残さなかったので、完全に忘れ去ってしまっていました。
とにかく、カフカの描く作品は不穏な空気の漂うおかしなものばかりですが、それだけオーストリア帝国は国民を虐げていたのではないか、と思います。自由のない、圧政の国。そこでなんとか生きていくために、カフカは筆をとり続けたのか?ただ、不思議なことに、小説からは絶望的な感じがしないのです。『城』もそうだったのですが、どう考えても主人公が置かれている状況は最悪だし、絶望的なものなのに、どこかユーモラスに感じる。とことん暗く描くこともできるはずだけど、それぞれの登場人物が個性的でおかしくて意味不明だから、暗い気持ちになるよりは、クスッと笑ってしまう。腹がたつ状況のはずなのに、喜劇のように感じてしまう。それがカフカの偉大なところなのかもしれません。悲劇を喜劇に昇華できるというか・・・。しかもブラックユーモアで。私たちが、普通は同情し、応援したくなるはずの主人公もまた、おかしな人だからそこまで感情移入もできない。Kも、相当変な人なので・・・。
カフカは、好き嫌いは分かれそうですが、病みつきになるタイプの作家ですね。彼の作品を理解するのは決して容易ではないけれど、彼の置かれていた国の状況、家族や人間関係などの背景が見えてくるとわかりやすいかもしれない。次は、またしても未完の『アメリカ』に挑戦してみたいと思います。
最後に、『審判』は他の長編小説と同様、カフカの友人マックス・ブロートにより、カフカの死後出版されました。カフカは遺言で、すべての遺稿を焼却するようにと頼んでいたのですが、ブロートはそれには従わずに出版。ブロートが遺言通り焼却してしまっていたら・・・。カフカの一部の作品群は永遠に誰にも読まれるこのないまま、この世界から完全に消滅してしまっていたことでしょう。
原題:Der Proceß
出版:1925(執筆1914-1915 )
